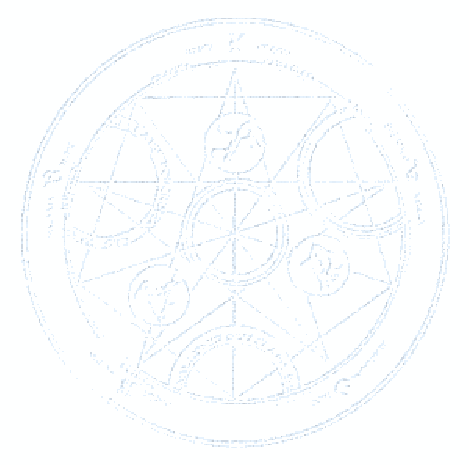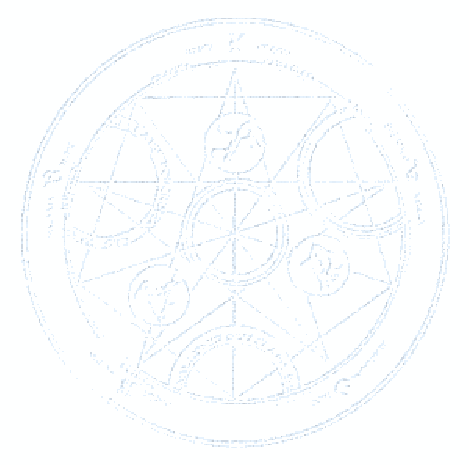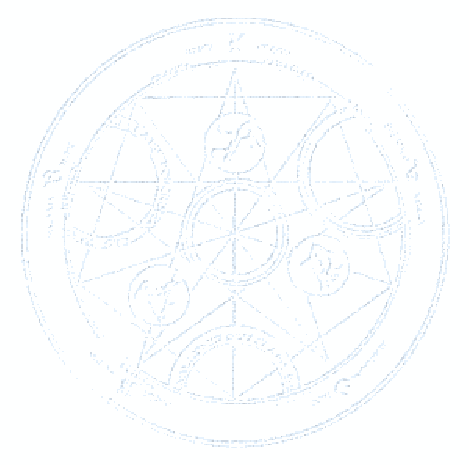

わたしの名はラサ=カーラという。
今は人の姿を取っている。
だが、わたしは人ではない。
わたしの本体は炎竜である。
我ら竜族は、内なる炎の力をもって、姿を自由に変えることができる。
しかし人に姿を変えるのは、非常に困難なことだ。
竜族の中でも、よほどの上位の者でなければ、自身の力だけで長く人の姿を取ることはできない。
わたしには、幸いなことに、まだそれを成しうるだけの力があるのだが。
(だがこれでも、人にはわたしの姿が恐ろしく見えるらしい。
と我が君はおっしゃっている。
もう少し見れるようにしようと思えば、できることはできるのだが、
ものの数時間も経たぬうちに、息切れしてしまうだろう。
とても我らの王と姫のようにはいかない)
わたしがそこまでして姿を変えているのは、二人のご主人のお傍近くに仕えるためだ。
なのだが。
……そのわたしは今、少々、不本意な状態に置かれている。
「もう少し!
もう少しだからねー!
もうちょっとで、できるからねー」
わたしの二人のご主人、ヴァルナさまとレスさま。
わたしはお二人のためなら、例え火の中、水の中。
妖精族の井戸端会議の中にも飛び込んでみせる覚悟だ。
「あ、ラサさん、止まってっ」
レスさまの容赦のない静止の声に、わたしの手は、空中で直ちに動きを止めた。
「今、さりげなく、こしょうを取ってくれようとしたでしょう。
うれしいけど、だめだよ。
わたし一人で作りたいんだから」
アヴェスタ王国を出てからすでに数ヶ月。
これまでは宿屋や船に宿泊してきた。
しかし奥深い森に入って野宿することになり、必然、自炊しなければならなくなった。
わたしたち竜族は手先が器用である。
どうも主を定めると、その器用さがさらに際立つようになるらしい。
特に掃除・洗濯・料理・裁縫は得意中の得意である。
もちろん、今回も腕によりをかけて、わたしが作った食事をお二人に召し上がって頂こうと思っていた。
「だめだめ。
明日はわたしがごはん、作るから」
「しかし」
「だめだめ、作りたいんだよ。
お願い、作らせて」
「では」
「だめだめ、手伝うのもだめ。
ラサさんは見学。
いい?絶対だかんね」
「………」
レスさまは断固として、わたしが手伝うことを許してくださらなかった。
なぜだ。
……なにか粗相をしてしまったのだろうか……
そういえば、以前からレスさまは何かと身の回りのことを、お一人ですませてしまいたがるたちだった。
料理もたいへんお上手だ。
(当たり前だ、なにしろわたしのお仕えしているご主人なのだから)
…しかし。
だからこそ、むしろわたしの手助けがわずらわしくなってしまわれたのかもしれない。
やりすぎてしまったのだろうか。
わたしの気持ちが重くなってしまわれたのだろうか。
もうわたしなど、邪魔になってしまわれたのだろうか…
「あー、ラサ、ラサ。
ちがうちがう。
そういうことではない」
「…………」
「そんな子犬みたいな目をするな。
正体はあんなにデカイ図体をしているくせに。
そういうことではないと、言っているだろ」
「…………」
「あー、それからな。
その手も、もう下ろしていいと思うぞ」
「できたー。
おまちどうー」
にこにこしながら、レスさまが食事を持ってきてくださった。
シチューにサラダ、それからパン。
ドライフルーツを使った、ケーキまで。
「おおー、すごいな。
ごちそうだな」
「へっへー、がんばっちゃったよー。
なにせ、これくらいしか取りえがないからねー」
「そんなことはないぞ」
「ま、いいから、食べて、食べて。
それで感想を聞かせてよ」
これは覚悟を決めて食さなければならない。
なにしろ、ご主人が自ら作ってくださった食事だ。
わたしたち竜族は、何日も食事を取らずに過ごすこともできる。
だが、ご主人が作ってくださった食事ともなれば、話は別である。
手渡された匙を手に、わたしは一口、シチューを食した。
「…………」
「どう?」
「…………」
「ひょ、ひょっとしてまずい?」
「とんでもございません。そんなことはありえません。たいへんおいしゅうございます。絶品です。極上です。
感激のあまり、言葉を忘れてしまったほどでございます。
もうこれ以上はないというほど、美味でございます。塩加減といい、とろみ具合といい、文句のつけようがございません。
世界一です。宇宙一です。さすがでございます」
「…あ、ありがと。
でもそれはちょっと、いいすぎじゃあ」
「はっ。
申し訳ございません。
あまりの素晴らしさに、つい、正直な感想を述べてしまいました」
「あ、あはは」
レスさまは、それからヴァルナさまの方に向き直った。
「……それで……
ヴァルナは、どう?」
「うん………おいしいな」
「ほ、ほんと!?」
「うん、うまい」
「………」
「レス?」
「あ、あはは。
なんかめったやたらと嬉しくて」
「………」
「もしかして、人生で1・2を争うほどうれしいかも…
って、ちょっと大げさだね。
わたしもラサさんのこと言えないね」
昔。
レスさまは忘れていらっしゃるはずの、遠い昔。
皆で旅をしていたあの頃、野宿をする機会は今よりずっと多かった。
その中で食事の用意を担当するのは、主にヴァルナさまとアルダシール王だった。
途中からわたしや白の魔女が同行するようになり、その任を担うことになった。
レスさまは、よく申し訳なさそうなお顔をなさっていたものだ。
「ごめんね、ラサさん、アラベラさん。
いつもいつも、ごはん作ってもらっちゃって」
「いいのよ。
レスは小さい頃からずっと、剣の稽古をしなくちゃいけなかったんだから、仕方ないでしょ」
「いや、むしろレスの作る食事は特徴ありすぎるっていうか、あれだし」
「おのれ貴様、アルダシール!
レスさまを愚弄するか!」
「愚弄もなにも、本当のことだろ。
王族のおれより料理ができないって、どうなんだよ」
「う、く、く……
そ、そのうちできるようになってみせる!
練習しさえすれば、わたしだって!」
「練習ってお前、いつ練習すんだよ。
おれはやだぞ、お前の練習台になるなんて」
「む、ぐ、ぐ、ぐ……そのうちはそのうち!
平和になったら!
それが無理なら、生まれ変わってでも料理上手になってやる!
見てろー!」
「生まれ変わってって、おま……そんなの、どうやって確かめろってんだよ」
「ふ、くく……」
ただひとり、ヴァルナさまだけがそれに笑って答えた。
「お前なら、きっとその約束を守ってみせるだろうな。……
楽しみにしてるよ」
「うん、このパンもうまいなー。
売れるな、これは」
「ほんとー!?
わーい、ありがとー。
ケーキも食べて、食べて」
「まてまて、まだこっちが残ってる」
あの頃から、レスさまは決して約束を違えない方だった。
わたしはその約束が果たされた場面に立ち合えたわけだ。
その上、ご主人の作った食事まで口にできた。
竜族冥利に尽きるとは、まさにこのことだろう。
しかし……困った……
レスさまが作った食事を食べたいと思うなら、わたしは食事を作れないということではないか。
ご主人に料理をさせて自分は何もしない、というのは、竜族としてはどうにも耐え難いものだ。
しかし、このシチューは美味である。
食せるものなら、これからもぜひ食したい。
わたしは以後、どうするべきだろう。
…作るべきか…
…作らざるべきか…
Fin

「レスのお料理大作戦」