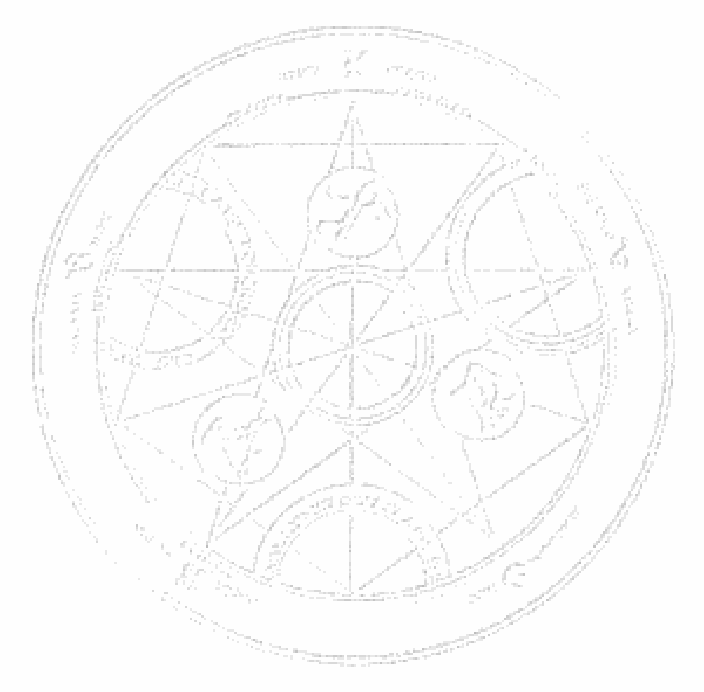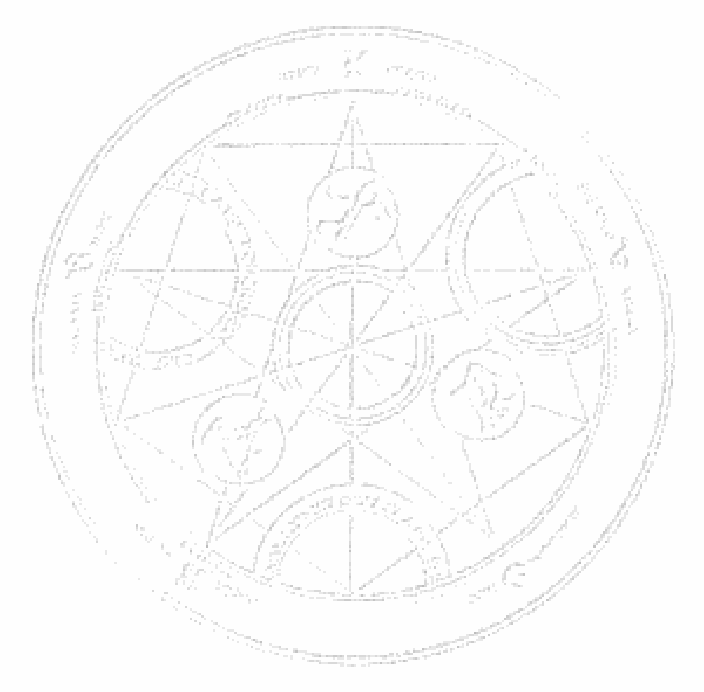女王様のお料理大作戦
「陛下は、今朝から厨房にこもっていらっしゃるのですね?」
窓際の椅子に腰掛けていた彼が振り返る。
その表情を見ておや、とアラベラは思った。
さりげなく、暖炉から距離を取る。
(機嫌が悪くていらっしゃるわ)
二年前、女王の即位式の直後、彼女に仕えるために、アラベラは王宮に出向いた。
そこに彼の姿を見つけたときの大きな驚愕は、今でもはっきり覚えている。
昔、ずっと以前に一度だけ、彼に会ったこともあった。
そのとき、アラベラはほんの短時間しか、彼を直視することができなかった。
今でも、女王や師であるあの人が、よくもあんなに平然としていられるものだと、感心せずにはいられない。
親愛と畏怖の念とは、また別のものである。
「今朝だけではない。
近頃、ずっとだ」
「問い正されなかったのですか?」
隠したがっておいでだったと、やや不明瞭に答えが返ってくる。
アラベラは思わずくすり、と笑ってしまった。
これほどの力を持ちながら、まったく竜族というのは不思議な種族だ。
主に対しては、子犬よりも大人しく従順に、かわいらしくなってしまう。
気になるのなら問いただしてしまえば、一言ですむのに。
要するに、彼は主にかまってもらえなくて寂しいのだ。
と思いながら、アラベラはその辺りでやめておくことにした。
竜族の気の短さと怒ったときの恐ろしさは、身にしみてよく分かっている。
かわりに足元にうずくまっていた子猫を抱きかかえる。
やはり不機嫌そうなその様子に、アラベラは再びくすり、と笑ってしまった。
「失礼。
陛下が厨房から出てこられたましたぞ」
ノックの後に、じいやのベン=ネビスがあわてて部屋に入ってきた。
「あらまあ、やっと。
それで12時間も、一体何をしていらしたのかしらねえ?」
「そそそ、それが」
じいがうわずった声を出した直後、女王がひょこっ、とその後に顔を出した。
「ぬおおおおおおっ、陛下っ」
「料理に決まっておる。
厨房ですることなど、他にあるまい」
「我が君」
「おまたせ、ルアーダ。
すまぬ、時間がかかってしまった」
「料理など、わたしが致しましたものを……」
「結婚して以来、ずっとルアーダが料理をしてくれているではないか。
以前は料理長に遠慮していたものを、もうその必要もない、などと申して。
まあ……よいから。
とにかく、座れ」
彼をうながして、女王は持っていた皿の上からふきんを取った。
のぞきこんだ一同は、そろって瞠目した。
「まあ……クッキー」
しばらくして、アラベラがようやく口を開いた。
「クッキーに見えますな……」
「これを作っていらしたの」
「いつもしてもらってばかりでは不公平だと、前にも申したであろう」
「……わたしに?」
たっぷり10秒ほどたってから、ルアーダがやっと言った。
「そうじゃ、ルアーダへのプレゼントじゃ。
一度くらいは、わらわだって何かを作ってそなたに馳走したい。
料理が苦手だという自覚があるから、ここ最近、料理長に頼み込んで練習していた。
形よく作れたものは、これだけだったのだが」
「これだけできれば、十分ですわ、陛下」
「そ、そうか。ありがとう」
「ううむ、一応クッキーには見えるが……しかし十二時間かかって、これだけ……」
「しいっ、じいやさん!」
「………」
「その……ルアーダ。
食べてみてくれるか」
「もちろんです」
ひとつをつまんで、ルアーダはさく、と一口かじってみせた。
「ああっ、なんの躊躇もなく!
ルアーダ様、大丈夫でございますか!?」
「ル、ルアーダ!
まずかったらぺっしてもよいからな。
ぺっしても!
そなたの体の方が大事じゃから!」
ルアーダは続いて二個目を口に放り込んだ。
その顔が、幸せそうに微笑んでいる。
「最高です」
「…………
……ほ、ほんとうか」
「これ以上のものはありません」
そしてルアーダは、彼女だけにしか向けないやさしい目で、にっこり笑った。
「世界一のクッキーです」
「おおー、やった―!
ルアーダに料理でほめられた―!」
「な、なんと!
では見かけだけでなく、けっこういけるのか……?
その〜、ルアーダ様」
「はい」
「わしにも一つだけ……」
「だめです、わたしのものです」
「即答ですかっ。
いいではありませんか、ひとつだけ!
全部くだされとは申しておりませぬのに」
「だめです」
「そこをひとつ……」
「だめです」
「なんとか」
「だめです」
「ルア」
「だめです」
「とと、途中でさえぎるなんてひどいっ。
いいではありませんか、せめて一口だけでも!
この間まで同僚だったんですぞ、あまりにもつれなさずぎます――!」
「ちょ、じいやさ……」